こんにちは。
立教大学人工知能科学研究科M1としての第12週を終えました。
今週は、授業が最終テーマの「最適化」に突入し、
研究ではついに初めての定例ミーティング発表が決定。
自己学習も引き続きPyTorch系のフレームワーク理解を深めています。
今週の授業・ミーティング参加状況
6/17(月)
-
情報科学概論(録画視聴)
6/18(火)
-
機械学習(録画視聴)
6/20(木)
-
研究室 定例ミーティング(録画視聴)
6/22(土)
-
数理科学概論(録画視聴)
-
機械学習演習(録画視聴)
■ 情報科学概論(月)
今週はネットワークと暗号化がテーマ。
-
プライベート / パブリックIP
-
公開鍵 / 秘密鍵方式
など、インターネットの基盤技術について学びました。
普段意識せず使っている仕組みの裏側を理解できて、非常に興味深かったです。
■ 機械学習(火)
先週は分類理論(ロジットや識別関数など)を学びましたが、
今週はその理論をPythonコードでどう実装するかという内容に進みました。
やはり、数式だけで終わらせず、実装に落とし込んでこそ理解が定着するなと実感しています。
■ 研究室 定例ミーティング(木)
今週は学生の発表がなかったため、教授がご自身の研究について紹介されました。
テーマは具体的には伏せますが、応用先のある興味深い研究で、
「こういうアプローチもあるのか」と刺激を受けました。
■ 数理科学概論(土)
いよいよ講義も終盤戦に突入。
今週からは最適化にテーマが移りました。
まずはその全体像(概要)を丁寧に解説いただき、
今後扱うであろう勾配法やラグランジュ法などの前提となる考え方を確認できました。
■ 機械学習演習(土)
今週の演習ではテキストデータの分類を実装。
講義中はロジスティック回帰、課題はSVC(サポートベクターマシン)を用いたものでした。
テキストの前処理、ベクトル化、分類器構築と、
実務に近いプロセスをシンプルに学べる良い演習でした。
研究活動
今週はエラー分析に取り組みました。
-
どのクラスで誤分類が多いか
といった視点で整理し、教授に報告したところ、
「ぜひ一度、定例ミーティングで発表を」とお声がけいただきました。
来週、研究室メンバー全体に向けた初の発表を予定しています。
緊張もありますが、しっかり準備して臨みたいです。
自己学習
引き続き、
『ゼロから作るディープラーニング③ – フレームワーク編』
に取り組んでいます。
-
全60チャプター中、現在10チャプター目
-
クラス設計や内部構造を理解でき、PyTorch導入に向けた準備として◎
単にAPIを使うのではなく、
なぜこの構造になっているのかを知ることが、今後の応用力につながると信じて取り組んでいます。
今週のまとめ
今週は「最適化」という大きなテーマに突入したことで、
学問としての機械学習の核心に一歩近づいた感覚があります。
また、研究では初の発表準備に入るという重要な節目。
説明資料づくりにも力を入れて、しっかり伝えられるよう頑張ります。
それでは、また次週!


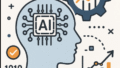
コメント