こんにちは。
立教大学人工知能科学研究科M1としての第8週を終えました。
今週は、研究の進捗が一歩前進し、いよいよコード実装フェーズに突入しました。
授業では重回帰分析や偏微分など、理論と実装の両面で学びが深まりました。
今週の授業・ミーティング参加状況
5/20(月)
-
情報科学概論(Zoom参加)
5/21(火)
-
機械学習(録画視聴)
5/23(木)
-
研究室 定例ミーティング(録画視聴)
5/25(土)
-
数理科学概論(録画視聴)
-
機械学習演習(録画視聴)
■ 情報科学概論(月)
今週はプログラミング言語の概要について。
コンパイラ型とインタプリタ型、各言語の設計思想など、普段なんとなく使っている言語にも背景があることを改めて実感しました。
■ 機械学習(火)
重回帰分析と共線性について学びました。
変数間の多重共線性がモデルに与える影響や、その回避手段についても触れられており、統計的視点が求められる内容でした。
■ 研究室 定例ミーティング(木)
学生による研究の進捗報告を視聴。
それぞれの進み方やテーマの違いを見ると、自分の取り組みにも刺激になります。
■ 数理科学概論(土)
偏微分がテーマでした。
変数が複数ある関数を扱う数学として、今後の機械学習や物理モデリングでも必須になる内容です。
また、1回目の課題提出もあり、無事完了しました。
■ 機械学習演習(土)
今週は**重回帰分析と正則化(L1・L2)**の実装に取り組みました。
チューニングを通じてモデルの精度を向上させることが課題。
試行錯誤したものの、ごくわずかにしか精度が上がらず、パラメータ選びの難しさを痛感しました。
逆に言えば、それだけ過学習やバイアス・バリアンスのバランスを考える必要があるということですね。
自己学習
■ 生成モデル(拡散モデル)
先週から取り組んでいた拡散モデルについて、今週で一通りの読み込みとコード実装が完了しました。
理論と実装の両方に触れられたことで、理解もだいぶ深まりました。
また必要になったタイミングで再読しようと思います。
研究活動
ついに一歩前進!
データセットを収集できました。
GitHubで目的に合致しそうなデータを見つけ、使用の可否を確認したところ、問題なしとの返答をいただきました。
これでようやくコード実装に着手できるフェーズに入りました。
来週以降は、実践的な内容に進んでいけそうです。
今週のまとめ
授業では偏微分や正則化といったテーマを通して、理論の深堀りと実装の両方に取り組む週となりました。
また、研究活動もいよいよスタートラインに立ち、ここからが本番といった感じです。
焦らず、一歩ずつ進めていきます。
それでは、また次週!
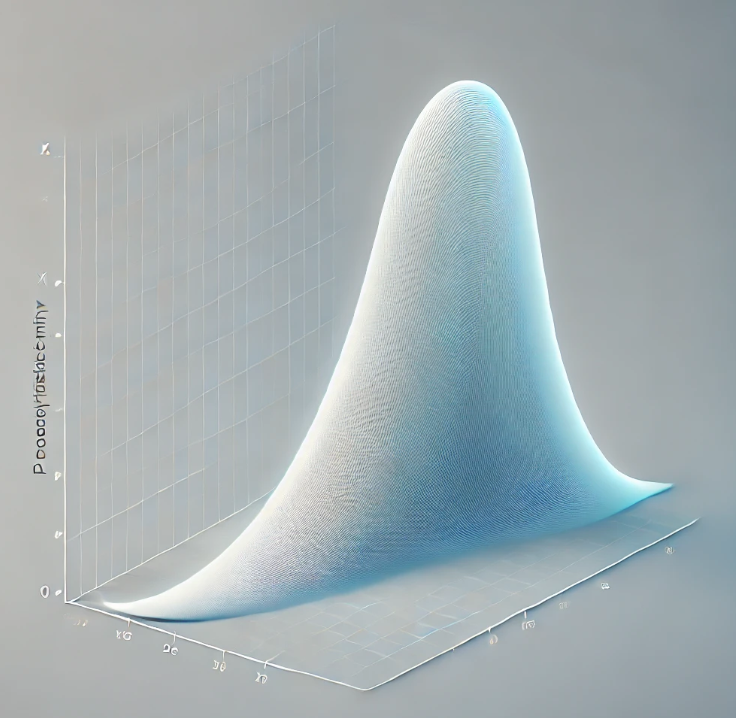


コメント