こんにちは。
立教大学人工知能科学研究科M1としての第9週を終えました。
今週は、研究における初期モデルの実装と精度検証が完了し、
いよいよ「改善フェーズ」に入っていく大きな節目の週となりました。
授業や演習でも、より実践的な内容が増えてきています。
今週の授業・ミーティング参加状況
5/27(月)
-
情報科学概論(録画視聴)
5/28(火)
-
機械学習(録画視聴)
5/30(木)
-
研究室 定例ミーティング(録画視聴)
6/1(土)
-
数理科学概論(録画視聴)
-
機械学習演習(録画視聴)
■ 情報科学概論(月)
今週は**データ構造(スタック・キュー)**について学びました。
CSの基本とも言える内容で、改めてデータ構造がアルゴリズムや効率に与える影響を実感しました。
■ 機械学習(火)
重回帰分析における過学習と正則化について。
前週の内容をさらに深め、L1・L2正則化の役割やハイパーパラメータ調整の重要性を再確認。
実務でもよく出てくるテーマなので、今後にも活かせそうです。
■ 研究室 定例ミーティング(木)
学生の研究進捗報告に加えて、学会発表の様子なども共有されていました。
発表に向けてどう準備していくか、という視点でも刺激を受けました。
■ 数理科学概論(土)
多変量の勾配、ヤコビ行列の導出がテーマでした。
スカラーやベクトルをベクトルで微分するとどうなるかという部分を、
数学的にしっかりと理解できるようになる良い講義でした。
■ 機械学習演習(土)
今週の課題はかなり実践的です。
重回帰分析にPCA・交差検証を組み合わせてモデル精度を向上させるというもので、
現在取り組み中。モデルの構成や評価方法の設計で悩みながら進めています。
自己学習
今週は以下の内容を自主的に学習しました:
-
最適輸送アルゴリズム
-
ラグランジュの未定乗数法
最適化問題に関する理論の復習が中心でした。
研究や応用数学に関連するので、再確認しておいてよかったです。
研究活動
大きな一歩!
ついにモデルの初実装 → 精度評価まで完了しました。
幸いにも、初期段階としては悪くない精度が出ました。
その結果を教授に共有したところ、以下のようなフィードバックをいただきました:
-
一部アーキテクチャの修正ポイント
-
Pytorchの使用(現状kerasを使ってました)
それらをもとに、来週からモデルのブラッシュアップに取り掛かる予定です。
今週のまとめ
今週は、授業・研究・自己学習のどれもが「深まり」の週でした。
特に研究で初期モデルの評価までこぎつけたのは、自信にもつながる成果でした。
来週からは再設計→再検証のループに入っていきます。
一歩ずつ、丁寧に取り組んでいきたいと思います。
それでは、また次週!
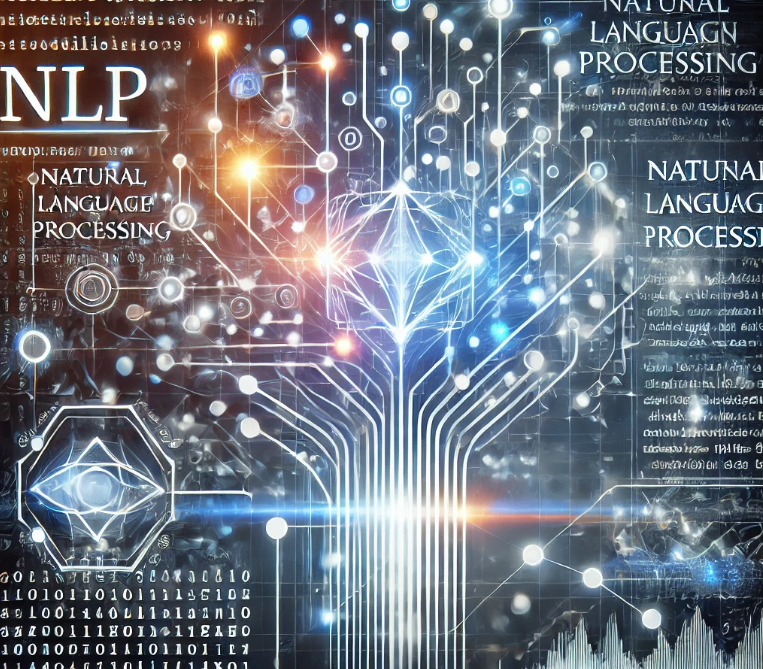
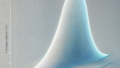

コメント